2020/02/22 【石文化対談】
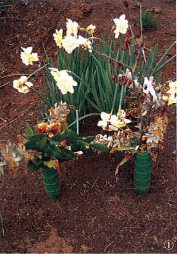
平地に埋葬された土葬のお墓
加地:これを「神道碑」というです。それは霊魂がお通りなさる道でもあるわけなんです。そこが大切なんです。けれども墓域の規模が小さくなってくると、この神道碑を墳近くに立てて、しまいには墳の前に建てるようになった。そういう形式が中国でも朝鮮半島でもあります。 同じように日本でも墳の前に神道碑が建てられたわけですが、それがさらに墳の上に載るようになった。これはほんらい自然石だったのが、やがて白い石になりますね。その上にのっただけのことなんです。だから日本の石塔の原型は神道碑を墳の上に意のせてできあがったんですよ。
吉田:ほおー。

盛り土に石を積んだ「墳」のお墓

平地の埋葬地に石塔が建てられる
加地:お寺では、これを地・水・火・風・空とか縁づけていますが、ほんらいの意味はそういうことなんです。それが江戸時代には1つのシステム化された形になってきて、石の個人墓になった。それがやがて家墓になっていきます。家墓はごく最近にあらわれたものなんですね。これは、完全土葬がなくなってしまったことも関係があります。昔はそのまま土葬することが多かったですから個人墓ですよ。今は荼毘にふして、遺骨式になっている。遺骨を納めるお墓になって小さいですよね。だからよけい家墓になってきた。骨壷を家族で納めて、墓誌を一つにする。それがここ数十年来の家墓の大流行なんですよね。
「葬送の自由をすすめる会」の連中は、昔はお墓が無かったなんて馬鹿なこと言っていますが、庶民のものは平地の「墓」だったから見えないだけですよ。小さな石を置いたケースもあったわけですが、だれかが放ってしまえばわからない。それを理由にして、お墓はいらないなどと馬鹿なことを言っている。

神道のお墓

「墳」の上に石塔が立つ 教派神道のお墓
人間は死者を葬るという点では、ずうっと変わってない。それは人間らしいところです。人間が猿や犬や猫、他の動物と決定的に違うところは、はっきり言えばそれだけです。じゃ誰が葬るのかといったら、いちばん近しい者が葬るのが当たり前でしょう。その一番近しい者とは血がつながった者、昔は一族。だんだん小型版になって、いまのように小家族になってきましたから、小家族するというふうになったんでしょうね。これはこれからも続くでしょう。本来で言えば、きちっと葬りさえすれば、墓碑・墓塔は必要ないんです。平地のふつうの「墓」でもいいんです。